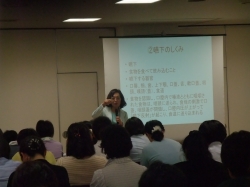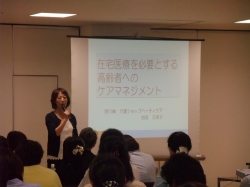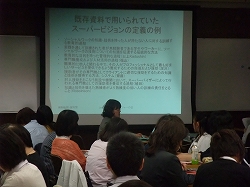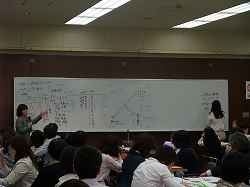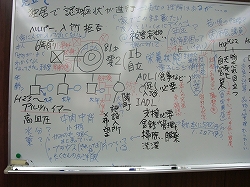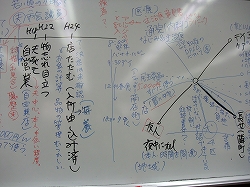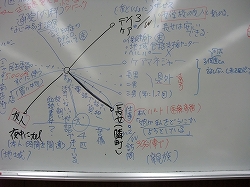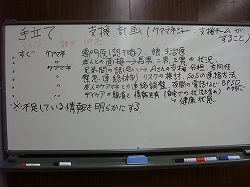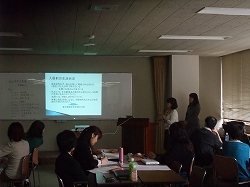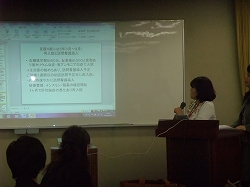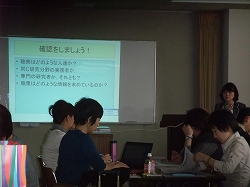■日 時:平成25年4月13日(土)・14日(日)
■場 所:愛知県青年会館
■参加者:会員13名 内認定ケアマネジャー10名
第Ⅳ回 学会発表支援塾 実践編(2)に参加して
医療法人順和 トータルケアプラン21 下田智子
今回学会発表支援塾を入門編から実践編(1)(2)と最後まで受講させていただき
ました。
段階的に事例研究の方法を学び、実践編(2)ではパワーポイントの作成やプレゼン
テーションの実際等勉強させていただきました。
事例研究に慣れない私は、抄録も内容が不十分なままで今回の研修に参加することに
不安がありました。1人で作業していると、自分の事例で一番言いたいことが何か見
えなくなってしまったり、視野が狭くなっていました。
今回パワーポイントで視覚的にどう示すのか、また何をどのように伝えていくのが効
果的なのか、等とても難しかったですが、参加者の方々の事例やパワーポイント、模
擬発表からたくさんのことを学ばせていただきました。参加者の方々や理事の先生方
のご意見、アドバイスを頂いて客観的に事例をふりかえることができました。学会発
表までに修正し抄録内容の遅れを取り戻せるよう努力したいと思います。
全国から参加しているケアマネジャーの皆様と一緒に学ぶことができ、勇気を頂きま
した。今後も自分の支援を客観的に振り返る、そして支援を言語化することを自分の
課題とし、ぜひ来年も参加させていただきたいと思っております。理事の先生方、今
後ともご指導のほどよろしくお願い致します。
ピアリング堺 佐藤 笑美子
1月、2月、4月と日本ケアマネジメント学会の研修に参加しています。
過去、医療職として、毎年自身の振り返りとしての学会発表等があり大変でしたが、自
身の役割意識の向上、モチベーション維持に役立っていたと思います。
ただ、量的研究の経験だけで、質的研究(事例発表)は初めてで、福祉における質的研
究発表について一から勉強するつもりで参加させていただきました。
在宅で支援させていただくようになって、自分で自分がやりたいことをやりたいと日々
悩みながら慌ただしく日々に流されています。
福祉(誰もが当たり前に享受できる幸せ)に関わる方々が、ご利用者様の最善の利益を
考えられているか、福祉マインドをお持ちであるか、そうであれば相互に共通の使命に
向けてモチベーションを高めあえるのですが、そうばかりでないのも現状です。
どうしてこのようなことが行われているのか、自分の責務を果たそうとすればするほど
疲弊することもあり、モチベーションが低下することも多くあります。
2月に急遽(大きなエピソードがあり)発表内容を決めたので、プレゼン資料つくり
に、ご指導、ご助言をいただくに当たり、学会発表支援塾、ひまわりの弁護士さん、リ
ーガルサポートの司法書士さん、ぱあとなあの社会福祉士さん、地域包括支援センター
や保険者の方、みんなが師になっていただいています。
今回の学びを糧に、発表を頑張りたいと思います。